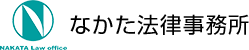旧コラム
現在のコラムはこちらから
租税憲法と租税回避行為 [税法の話2]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回は租税憲法と租税回避行為についてのお話です。
【租税法律主義】
租税法律主義は、憲法84条、30条に定められています。
租税を課すには法律の規定が必要なことは、国民の財産権を定める憲法29条から当然です。
課税権の制限が立憲主義の原動力となったという歴史的背景があって、憲法に2条も規定がおかれているのです。
そのため、租税法律主義は、刑罰権の制限である罪刑法定主義と同様非常に大事な原理になります。
考え方も罪刑法定主義とパラレルですが、財産権の制限という性質上、罪刑法定主義ほどは厳格に解釈されません。
租税法律主義は、課税要件法定主義、課税手続法定主義、課税(租税)要件明確主義、合法性の原則、租税法規不遡及の原則を要請するとされます。
なお、無限定ではないですが、法律には条例も含まれます。
課税要件法定主義
課税要件は法律で定められなければいけません。当然ですね。政令、省令などに、重要な点を丸投げしてはいけません(包括委任の禁止)。
課税要件とは、①納税義務者、②課税物件(対象行為、物、事実)、③課税物件の帰属、④課税標準、⑤税率です。
税務通達は、国税庁長官から職員に対して発出される命令(国家行政組織法14Ⅱ)にすぎません。法令解釈通達、執行通達、事務運営指針(加算税通達)です。法律とは扱われません(通達課税の禁止)。「法律ではなく通達による課税」ということになれば違法になります。
ただし、法律に何ら根拠のないレベルにあることが実務上要請されます。判例でも、「課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、法の根拠に基づく処分」とされています。裁判にあたっては、あくまでも法律の解釈がなされます。通達は参考規定にすぎません。通達に沿った課税は、根拠法令の立法趣旨に照らして合理性を厳格にチェックされます。
課税手続法定主義
課税要件だけ法律で定められていても、課税手続が法律で定められなければ適正手続が保障されません。
課税手続も法定されることが要請されます。罪刑法定主義と同じです。
課税(租税)要件明確主義
租税法の定めはなるべく一義的で明確でなければいけません。
曖昧な規定では、租税法の
①公権力の濫用防止機能、
②予測可能性、法的安定性確保機能、
を果たせません。
租税負担の増大化、及び経済活動の高度化・複雑化に伴い、租税法律関係の予測可能性と法的安定性の確保が重視されるべきとも言われます。申告納税制度ですから、租税法は国民のマニュアルですからね。
したがって、租税法解釈をする際には、文言の明確性を崩さない手法をとらなければいけません。拡張解釈は許されません。現実には、「(不)相当」「正(不)当」などの文字からは具体的にどういう場合に適用されるかわからない「不確定概念」が多用されています。担税力に応じた実質的公平をはかるためには合理性があり、法の趣旨・目的からその意義が明確化できるなら問題がないとされます。
合法性の原則
課税庁は、課税要件が充足されている限り課税するべきで、恣意的課税・徴収は許されません。法律の規定どおり課税しろということです。
したがって、課税庁は融通が利きませんし、裁判でも和解ができないとされます(ただし、合法性の原則の論理的な帰結ではないとされますが)。
租税法規不遡及の原則
課税するには法律の定めが必要ならば、法律ができる前の行為には適用されないはずです。ただし、罪刑法定主義とは異なり、合理性がある限りで遡及適用も許されるとされます。
所得税の分野で、特措法改正による長期譲渡所得損益通算不可とする改正を年度の初めに遡って適用した事例の判例があります。
最高裁は、合理的制約は許容されることを前提に、 駆け込み防止という合理的必要があり、所得税が期間税であること(既に発生した納税義務の内容を変更ではない)、報道等により予測可能だった等から、遡及適用を是認しました。ぎりぎりの例ではないでしょうか。
【租税公平主義】
憲法14条1項の平等原則から導かれます。「担税力」(納税能力)に即した課税を要請します。
所得税法における所得分類、超過累進課税がその最たる例です。
所得税では所得の種類(10種類)によって課税の仕方が違います。所得の種類によって担税力が違うということを根拠にしています。
超過累進課税制度も、勿論担税力に応じた課税の制度です。
【租税法律主義と租税公平主義の相克、租税回避行為】
租税法律主義と租税公平主義は場合によっては相克します。
法律の不備は立法で解決するか、公平を期すために租税法を柔軟に解釈して解決すべきかの問題です。
前者では文理解釈が要請されますし、後者だと目的論的解釈、拡張解釈が要請されます。ほかにも、通達への対応、規定がない場合の否認を許すか、についても対立します。
租税法律主義が憲法にはっきり定められている大事な原則である以上は、基本的には租税法律主義が優先します。
租税法律主義と租税公平主義の相剋の典型的な場面として、租税回避行為への対応があります。
節税とは、租税法規が予定した法形式を用いることです。軽減特例の利用などです。
脱税とは、課税要件充足事実そのものを秘匿することです。
租税回避行為は、節税でも脱税でもありません。
①通常のものと考えられている取引形式とは異なる取引形式を選択し
②通常の取引形式を選択した場合と同一またはほぼ同一の経済的効果を達成し、
③租税上の負担を軽減または排除することです。
税負担軽減目的は前提ですが、脱税という違法行為ではないのですね。
昔の典型的な例は、土地売買にかかる譲渡所得税負担軽減を目的として、お金が欲しい人が土地を欲しい人に対して極めて長期の地上権設定し、土地を欲しい人がお金を欲しい人に対して弁済期を地上権の終期とする時価相当額の金銭の貸付を行う。地代と利子は同額、一方的更新可能の例です。現在では通用しませんが。
様々な租税回避行為が、「節税スキーム」と称されて次々に考えられています。
法律を変えるのは大変、法律の抜け道を考えるのは簡単、ということで、いたちごっこになります。
そこで、法律の改正をしないで、当事者が用いた法形式を租税法上は無視し、通常用いられる法形式に対応する課税要件が充足されたものとして扱うこと(税法上の否認)が許されるかが問題となります。租税回避行為の否認の問題です。
租税法律主義の下では、法律の個別否認規定によらない否認は認められません。
租税公平主義からすれば似たようなことをしている者同士は同じ課税をするべきということになりますが、租税法律主義が優先します。
租税法律主義の下においては当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直し、それに対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁には認められていないのですね。
現在では、個別否認規定によらない否認は認められないことを前提として、私法上の法形式を租税法上もそのまま容認するかどうかが争われる傾向のようです(事実認定による否認)。
上の例では、地上権設定を売買として課税するというのではなく、私法上の契約が売買と認定される、売買と認定される以上は譲渡所得課税するという理屈です。法律解釈論(この場合も当該規定が適用されるか)ではなく事実認定(この場合はどんな契約が成立したか)で解決するイメージです。
租税の争いなのに、民法あるいは商法等の私法上どのような契約が成立したかの解釈で決着がつけられることになります。
勿論、簡単に認められません。私法上、法形式選択の自由が認められるのでどんな形式を遣おうが自由ですから。
次回は租税とは、租税法とは、といったお話です。そのあと所得税法のお話に入ろうと思っています。
お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
- カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 交通事故 (4)
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)