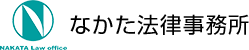旧コラム
現在のコラムはこちらから
可否同数の場合の議長の裁決権 [企業法務]
広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
今回の企業法務コラムは、議長の議決権を取り扱います。
取締役会、株主総会の通常の決議(過半数で行う決議)の場合、当然、議長は議決権を有することになります。
議長だからという理由で議長が議決に加われないとすると、その議決権を不当に奪うことになりますからね。
その他の団体の会議体でも同様に考えていいです。
一方、公的議会などでは、議長は決議に参加できず、可否同数の場合の決定票のみ有すると定められているようです。
議長は公正な立場でいなさいということでしょうか。
各種団体や会社で「可否同数の場合には議長が決する」というような決まりを定款等で定めている場合、どういう解釈をするべきでしょうか。
実際にあるようですね(会社定款ではこのような規定は認められないようですが)。
「可否同数の場合には議長が決する」の定めを、いったん議長が議決に加わった上で、可否同数の場合に再び議長が決定票を持つという解釈はできないでしょう。
議長が2個議決権を持つことになりますし、法定の決議であれば法定決議要件を勝手に緩和するものだからです。
そのような解釈でおこなった決議は無効となろうかと思います。
結局、「可否同数の場合には議長が決する」の定めは、議長はまずは議決権を行使せずに留保し、最後に議決権を行使することを定めた規定、というように解釈せざるを得ないでしょう。
もっとも、議長を交えた決議の結果として可否同数になった後に、改めて過半数決議等により「議長一任」の決議が成立した場合は別です。
適式に「一任」を内容とする決議が成立したことになりますからね。
そしたら議長が決めていいわけです。
もっとも、「取締役会での法定決議事項」などと法定決議事項全般について無限定に「議長一任」が認められるわけではないでしょう。
個別の議案に限ってということになると考えます。
こう見ていくと、「可否同数の場合には議長が決する」というような決め事は、あまり意味がないですね。
混乱させるだけのような気がします。
顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
- カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 交通事故 (4)
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)