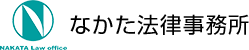旧コラム
現在のコラムはこちらから
会社運営と定款自治2 [企業法務]
広島市の弁護士仲田誠一です。
前回は、企業法務の話として機関設計の自由化の話をいたしました。
今回は、話が少し横道にそれるのを承知で、会社法との関係で機関に絡むトラブルやリスクを発生させるような具体的な事例の一端を、いくつかお話ししましょう。
まず、株主関係の話です。
会社法上、会社の所有者は株主です。社長ではありません。
最高意思決定機関も株主総会ということになります。
株主総会は、取締役会が存在しなければ一切の事項について決定権を持ち、取締役会がある場合には法定の決議事項と定款で特別に決めた事項に決定権を持つということになります。
最高意思決定機関である株主総会を構成する株主は、中小企業の場合、法人は例外で、ほとんど個人です。
人間であれば相続が発生するのですね。
それにより株式の共有状態が生じるかもしれませんし、株が外部流出する可能性もあります。
それにより、定足数の問題等で、株主総会の機能がストップするかもしれません。
そこで、事業承継対策は、株主の相続が発生しても、最高意思決定機関である株主総会が適切に開催され決議ができるようにしておくという面(株式あるいは議決権の集中、引継)が多くを占めています。
経営者様がいつ事故等に遭われて相続が発生するか誰にもわかりません。平時からの備えが大切ですね。
共同経営者を導入する際も、株式を引き受けてもらうのでしょうから、最高意思決定機関に生じるリスクを慎重に検討してください。
よく揉めます。
相続人等売渡請求規定には、買取資金を用意しないといけないリスクがありますので軽々に設定できません。
最終的には裁判所が決める時価での買取になりますからね。
株主が事故等で判断能力を喪失する場合、稀ですが行方不明になる場合も、相続と同じようなリスクが生じます(相続手続ができない分よりやっかいかもしれません)。
考えておかないといけないのは株主の相続だけではないのです。
名義株も整理しましょう。最高意思決定機関に絡むリスクは消しておきましょう。
有償あるいは無償の譲渡が通常でしょうが、株式併合による整理もあります。
名義株という証拠が用意できれば(名義株と認定するには諸要素が絡みます)、合意等なしでも消すことは可能でもあります。
今度は取締役です。
取締役が1人だと、取締役の急な相続、意思能喪失、行方不明の際に困ってしまいます。
取締役を1人にする場合にはそのリスクを認識する必要があるでしょう。
取締役の任期もある程度自由化されました。
しかし、再任手続が面倒だからといって単純に任期を長くすることはお勧めしません。
将来的に取締役を解任するには正当な理由が必要です、それがなければ役員報酬相当の損害賠償が必要となります。
任期を長くすればそれだけリスクが高まります。
経営者の離婚の問題もあります。単純に税金が安くなるからと言って、夫婦で平等に役員報酬を払っていたら痛い目に遭うかもしれません。
最後に、法定手続の瑕疵の問題です。
株主構成が単純でなければないほど、また機関設計が単純でなければないほど、会社法所定の手続も複雑になります。
法定手続を間違えると、決議取消の訴え、決議無効の訴え、決議不存在確認訴訟等により、効力が覆されたりするリスクが生じます。
仮に効力が覆されなくともトラブルが生じたこと自体で多大なコストを払わないといけません。
定款、種類株式、属人株式、遺言、株主間契約、買取り等の株式集中、株式併合等で、株主構成の単純化(株式集中)、機関設計の見直しを図ることをお勧めします。
次回は定款自治のお話をします。
顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
- カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 交通事故 (4)
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)