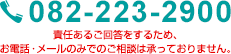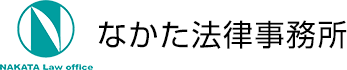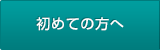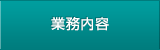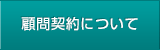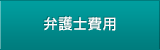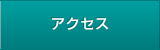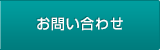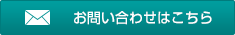最近のエントリー
カテゴリ
- 借金問題 (85)
- 相続問題 (57)
- お知らせ (3)
- 離婚問題 (31)
- 仲田 誠一 (238)
- 里村文香
- 桑原 亮
- 詐欺問題
- 交通事故 (4)
- 労働問題
- 不動産問題 (16)
- 身近な法律知識 (41)
- 企業法務 (70)
- 消費者問題 (11)
- 閑話休題 (6)
月別 アーカイブ
- 2022年6月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (5)
- 2021年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (10)
- 2019年8月 (8)
- 2019年7月 (11)
- 2019年6月 (11)
- 2019年5月 (11)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (25)
- 2019年2月 (20)
- 2019年1月 (24)
- 2018年12月 (25)
- 2018年11月 (18)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (3)
- 2016年8月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (6)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2011年2月 (9)
- 2011年1月 (21)
- 2010年12月 (25)
- 2009年9月 (1)
HOME > 旧コラム > アーカイブ > 2010年12月
旧コラム 2010年12月
現在のコラムはこちらから
「成年後見ってなぜ必要?」 2 【相続問題】
また,不景気が続いているからでしょうか,親のお金を当てにした人が起こす犯罪やトラブルも増えているような気がします。
公的年金も期待できませんし,これからの時代は老後について自己防衛をしていかないといけませんね。
さて,前回は成年後見の必要性について途中までお話いたしました,今回はその続きです。
◆ 将来の相続財産争いを防ぐ
将来の相続財産争いを防ぐために成年後見制度を利用するケースも多いでしょう。
相続争いの中でよく問題になるものとして,本人の判断能力に疑いがある時期の預金の引き出しや遺言の作成があります。
近い親族が,よくわかっていない本人を囲い込んで,自分に有利な遺言を書かせたり,預金の管理の名目で勝手に預金を引き出す例が,本当によくあります。
いざ,相続が発生すると,他の相続人は納得いきません,親族間の財産争いになります。
この点,成年後見制度を利用すると,裁判所の監督の下で,財産管理がされます。本人の判断能力がないなと感じたら,早めに成年後見制度を利用すると,一部の親族によるそれらの勝手な行為を防ぐことができます。結局,相続争いを防ぐことになるのです。
◆ 悪徳業者への対抗として
判断能力のない,あるいは乏しい高齢者を狙って,高価なものを次々と買わせたり(次々販売),だましてお金を取ろうとする詐欺行為が後を絶ちません。
そのような場合,成年後見制度(あるいはそれよりも程度の軽い保佐制度)を利用していたら,簡単に効力を否定することができます。
もちろん,それらの制度を使わなくても対処する方法はあるのですが,利用していた方が安心でしょう。
◆ 借金が見つかった!
認知症になった父に多額の借金があるのがわかったから自己破産などの債務整理をしたい,と言っても,本人に判断能力がなければどうしようもありません。
その場合には,成年後見人を選任してもらって,自己破産など債務整理をすることを考えます。
◆ 後見人は誰がなればいいの?
多くの場合は,親族や弁護士などを後見人候補者として予め決めてから,家庭裁判所に後見人選任を申し立てます。
候補者は親族でも,弁護士などの専門家でも結構です。
ただし,最終的には裁判所が後見人を選任することになります。推定相続人間で争いがある場合は,候補者を親族と予め決めておいても,第三者的な弁護士が選任されるケースが多いでしょう。
◆ 後見人になると大変ですか?
後見人は裁判所の監督に服します。だからこそ,本人の財産が適切に保全されるのです。
そのため,後見人は裁判所に対して各種報告書を提出する必要があり,その事務負担は軽いとは言えません。
なお,最近,本人の親族である成年後見人が,本人の財産を私消したため,業務上横領罪により逮捕されたという報道もありました。後見人は本人の財産を適切に管理する義務があり,自分のために勝手に使ってしまうと,業務上横領罪が成立し得るのです。
◆最後に
今回は制度の詳細までは説明できませんでした。細かい話は機会を見てお話します。
ご家族の現在あるいは将来のご本人の生活がご心配な方は,早めに弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
(なかた法律事務所)
2010年12月30日 00:18





「成年後見制度ってなぜ必要?」 1 【相続問題】
おせち料理も,いつからか食べなくなってしまいました。
県外出身の方はみなさん田舎へ帰ったりするのでしょうか。
残念ながら,私は実家が広島なので,里帰り気分も味わえません。
もっとも,親が近くにいる分,安心できる面もあります。
やはり故郷に高齢のご親族を残されている方はご心配でしょう。
ということで,今回は,高齢者に深く関係する成年後見制度について簡単にお話しようと思います。
◆ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは,日常生活を営むにおいて判断能力が乏しく助けが必要な方のために,裁判所が後見人を選任し,その後見人が,本人に代わって財産管理を行い,また身上監護事務(施設契約など)を行う制度です。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は,認知症患者であるなどの理由で,本人が常に判断能力がない状態にある場合に利用します。
任意後見制度は,現在は判断能力がある本人が,将来,自分がそれを失った時に後見人を選任してもらうよう,予め手当てをするために利用します。
◆ なぜ成年後見が必要なのですか?
そもそも何のために成年後見制度が必要なのか?がわかれば,成年後見制度がわかりやすいと思います。
簡単に言えば,成年後見制度があるのは,判断能力がない方には助けが必要だからです。
それでは,助けてくれる家族がいれば必要ないのではと思われるかもしれませんが,そうでもありません。
法律上,判断能力(意思能力)のない方はご自分では有効に契約などの法律行為ができません。
理屈は次のとおりです。
本人がする契約などの法律行為に本人が拘束されるのは,その契約などが自らの意思に基づくからです。
しかし,そもそも自分の行為が理解できない方が契約などの法律行為をしても,それは自らの意思に基づくとはいえませんね。
意思に基づかない以上,本人を縛ることはできない。
だから,その契約などの法律行為が無効になるのです。
ただ,そうなると,認知症などにより日常の判断能力がない方は,財産管理や施設との契約締結などを法的に有効にすることができません。
たちまち困ってしまいますね。
確かに,それらの行為を家族が本人に代わって行うケースも多いです。問題が起きなければそれでいいでしょう。
しかし,家族が本人に代わって行うそれらの行為は法的には問題があります。
判断の能力がない本人から頼まれたといっても,「頼む」(「代理権を与える」)ためにも本人の判断能力が必要です。
したがって,判断能力のない本人の家族が本人の「代理」で行った行為は基本的には有効にはなりません。
いざ相続が発生した際,「あなたが勝手にやったことだから無効だ!」と異を唱える相続人が出てきて,トラブルになるケースは決して少なくありません。
また,家族がいつまでも本人の面倒を見続けられるわけでもありません。その場合には,代わって面倒を見てもらう人が必要です。
さらに,判断能力がなくなると,不必要な高価な品をたくさん買ってしまい,財産を無駄に散逸させてしまいかねません。
そこで,財産管理や身上監護事務(施設の契約など)を,本人に代わり,ちゃんと(有効に)行う人物が必要になるのです。
◆ 最後に
成年後見制度の必要性は今回お話したことに尽きるものではありません。
将来の相続財産争いを防ぐために利用されるケースも多いですし,判断能力の乏しい高齢者を狙った悪質な次々販売などへの対処にもつながります。
次回は,そこら辺りのお話と成年後見人は誰がなればいいのかというお話しをさせていただきます。
(なかた法律事務所)
2010年12月29日 00:16





「ペットとマンション」 【消費者問題】
弁護士の仲田誠一です。![]()
今日はクリスマスですね。![]() 昨晩はよいクリスマスイブを過ごされましたでしょうか。私は,家族とトマト鍋を食べただけです。
昨晩はよいクリスマスイブを過ごされましたでしょうか。私は,家族とトマト鍋を食べただけです。
前回,クリスマスイブとは関係のない熱帯魚飼育の話をさせていただきましたね。
そういえば,以前に,よくあるマンショントラブルとして管理費問題をお話させていただきました。覚えていますか?滞納者が自己破産しても新しい所有者から回収できるなどお話しました。
今回は,熱帯魚の話をさせていただいたついでに,よくあるマンショントラブルの続きとして,「ペットとマンション」の問題をお話させていただこうと思います。![]()
![]()
◆ ペット飼育禁止の規約は守らないといけない?
ペットブームといわれて久しいですね。
ペット飼育OKの分譲マンションも増えてきたように思います。
ただ,まだまだ,ペット飼育禁止の規約があるケースが多いでしょう。たとえば,小鳥・魚類以外の動物の飼育の禁止や,他の居住者に迷惑・被害を及ぼす恐れのある動物の飼育禁止が,管理規約などで定められているのではないかと思います。
そのようなペット禁止規約は守らないといけないのでしょうか?
「自分のマンションだからいいじゃないか」と思いたくなりますよね。
実際に争われた事件もあります。
裁判所は,その中で,そのようなペット禁止規約の有効性を認めています。ペット禁止規約は,マンションでの平穏な生活の維持などのために合理的理由があるという理屈です。
したがって,ペット禁止規約は,守らなければなりません。
◆ ペット禁止規約に違反する住人に対して何が請求できる?
まずは,話し合うことになるでしょう。直接迷惑がかかっている居住者からは言いにくいので,管理組合として注意するのがいいでしょう。
おそらく,違反している居住者は,ペット禁止規約を知りつつ飼っている確信犯です。また,ペットを捨てろ,ペットを殺せというのか,とペットの命をかたに反論し,話し合いで解決しないかもしれません。
かといって,例外を認めてしまうと,規約がなし崩しになってしまい,ほかにも問題が生じるかもしれません。
では法的には何が請求できるのでしょう?
裁判所は,ペット禁止規約違反に対しては,厳しい態度をとっているようです。
違反行為に対して,禁止命令や損害賠償請求を認めたケースがあります。
そこで,あくまでも程度問題ですが,話し合いで解決できない住民に対しては,飼育禁止命令や損害賠償を請求することができることになります。
また,鳴き声,糞尿,悪臭などの程度が著しいケースでは,「共同の利益に反する行為」として,専有部分(つまり居室)の使用禁止なども請求できます。この点は,ペット飼育が認められているマンションも同様です。
◆ 「共同の利益に反する行為」とは?
先ほど触れた「共同の利益に反する行為」は,マンショントラブルの説明には欠かせない言葉ですので,ここで簡単に説明しておきます。
所有権者はその物を自由に使用・収益・処分できるのが原則です。この所有権の概念は,封建制度を否定した(何重もの土地支配を否定したなど)という歴史的意義があります。
でも,みんなが所有権の自由を主張すると,社会に混乱が生じて(たとえば隣地所有者の争いが多発します),社会生活が成り立たないのも現実です。そ こで,所有権自由の原則は,あくまでも原則であり,社会生活を維持するために一定の制限が加えられることは当然だと考えられています。
その所有権の制限が,分譲マンションにおいて顕在化しているのが,区分所有法6条1項であり,そこで,「区分所有者は,」「区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と定められています。
そして,区分所有法は,「共同の利益に反する行為」を行った区分所有者に対しては,差止請求,使用禁止請求および競売請求の3つの裁判上の請求ができるとも定めています。
なお,区分所有法上,「共同の利益に反する行為」をしない義務は,区分所有権者以外の専有部分の占有者(賃借人など)にも課されています。賃借人が義務に違反する場合にも同様な請求ができることになります。
◆ 最後に
次回には,マンションに関するトラブルでまだお話していないものを,ご紹介させていただこうと思います。
PS.先日,中学1年生の甥っ子が私のコラム,ブログを読んでくれていると聞きました。励みになりますね。![]()
(なかた法律事務所)
2010年12月29日 00:08





従業員は転勤を拒めない? 【企業法務】
みなさんの会社では,転勤の内示を受けるのはどれぐらい前でしょう?
今 は知りませんが,私が勤めていた頃の銀行は,転勤の直前に突然に転勤を知らされていました。もともと銀行は,癒着や不正を防ぐために定期的に転勤があるも のなのですが,直前に知らせることで不祥事を隠せないようにする配慮もあったようです。もちろん,家族持ちにはもう少し早く話が来ていたようですが。
さて,企業は自由に転勤を命じることができるのでしょうか?逆に言うと,従業員は転勤命令には絶対に従わないといけないのでしょうか?
転勤は,ケースによっては,企業側の業務上の必要性が,従業員の家族生活やキャリア形成の利益と衝突してしまう場面です。
最近読んだ法律雑誌に面白い記事が載っていたため,今回は,転勤命令のテーマをお話します。
◆ 企業に転勤命令権はある?
従業員に対する転勤命令権(法律的には「配転命令権」ということが多いです。)が企業にあるのでしょうか?
もちろん,勤務地・職種の限定がある労働契約を結んでいる場合には,従業員の合意がない限り配転はできません。一般的な契約の場合の話です。
少なくとも,就業規則上に転勤命令条項(転勤に関する条項)があり,勤務地限定の合意がない限りでは,企業側に転勤命令権が認められています。
就業規則の定めを確認しておいてくださいね。
◆ 企業は自由に転勤を命令できる?
結論を先に言うと,企業側に広い裁量が認められますが,完全に自由ではありません。
判例では,
① 企業側は業務上の必要に応じて,その裁量により広く転勤を命令できる,
② しかしそれは無制約ではなく,不当な動機・目的がある場合や従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を追わせる場合など,特段の事情がある場合には,企業の配転命令権が権利の濫用として許されない。
としています(表現は噛み砕いています)。
つまり,企業に業務上の必要性がある限りで,「原則」的に従業員に転勤を命令できるが,従業員にあまりにも不利益を与えてしまうようなひどい場合には,「例外」的にそれは許されないということです。
上に要約したのは,昭和61年の最高裁判決です。事例は,母の扶養や妻の仕事の都合から従業員が単身赴任を強いられるケースでした。
裁判所は,業務上の必要性を幅広く認めた上で,単身赴任を強いられるような不利益は従業員が普通に我慢すべきだから企業側の配転命令拒否を理由とする懲戒処分は有効だと判断しました。
◆ 最近の裁判所の判断の傾向は?
最近読んだ法律雑誌で次のような記事を読みました。
大企業では転勤命令に際して従業員の意向を確認する例が増えてきた。
また,最近の裁判例で,転勤に伴う従業員の新幹線通勤や単身赴任の不利益などを認め,企業側が敗訴する例が増えてきた,という趣旨の記事です。
時代は変わりつつあるようです。
従業員の健康,育児・介護を重視する法律ができ,家庭生活を重視する風潮も定着しましたね。
裁判所もそれを構成する裁判官は世代が交代していくわけです。それに伴い,時代にあった判断がされるようになるのです(かなりのタイムラグがあるのが通常ですが・・・)。
◆ 最後に
その当否は別として,会社に滅私奉公するという時代は既に過去のものとなっているようです。
企業の転勤命令も慎重に行使しないといけなくなったわけでして,それに限らず,企業のコンプライアンスも,その時代に合わせた対応をすることが必要なようです。
(なかた法律事務所)
2010年12月28日 00:30





「車は走る凶器?」 【身近な法律知識】
弁護士の仲田誠一です。![]()
年末もいよいよ押し迫ってきましたね。
例年,年末にかけて交通事故が増えるそうですね。日没が早くなったり,お酒を飲む機会が増えるからのようです。![]()
飲酒運転は絶対に止めてください![]()
◆ 車は「走る凶器」
ところで,法曹界では,車は「走る凶器」とよく言われます。
近代法が整備された頃にはまだ馬車の時代でした,車がなければ,悲惨な交通事故も当然ありません。つまり,自動車は人などにぶつかったら凶器になります(実際に自動車を凶器に使った事件もありますね),だから「走る凶器」なのです。
なぜ車が公道を走ることが許されているかというと,それは便利だからです。危険なだけのものであったら,法律で使用を禁止されるところですが,社会的に有用であるため,利用が許されているのです。車がない社会なんて想像できませんからね。
◆ 「危険責任」
危険な物を利用する者は,その利用に伴って生じた損害の責任を負うべきだ!という考えを「危険責任」論と言います。社会的に有用(必要)だから使ってもいいが,人に迷惑をかけたら危ないものを使っていたあなたが悪いから責任も取ってね,ということです。
危険責任の考えが背景にもあって,「車」対「人や自転車など」の事故については,そもそも車の責任の方が大きいと見られてしまいます。
具体的には,「過失割合」の話になります。事故の形態によって,ある程度の「過失割合」が決まっていますが,車側が高い設定になっています。
◆ 自賠責保険の存在意義
「自動車による交通事故の責任は,危険な物を利用している車の運転手側に多く負わせるべきだ」,といっても,運転手にお金がないと被害回復は結局実現しません。
そのためにあるのが,強制加入の自賠責保険制度です。
つまり,被害者に最低限の被害回復をする用意(それが自賠責保険)ができていなければ,自動車を運転させないということです。
◆ 任意保険にも入ってください!
それでは,自賠責保険に入っていれば安心なのでしょうか?
先ほど,自賠責保険は「最低限」の被害回復を保障するものであるということを書きましたが,「最低限」では足りません。
自賠責ではそもそもカバーできない被害弁償もあります。また,大きな事故だと金額も十分ではありません。
お金を惜しんで任意保険に入らなかったばっかりに,交通事故を起こして大変な目に遭う方も少なからずいらっしゃいます。
また,それではそもそも被害者に対して申し訳が立ちません。
さらに,事故についての刑事事件でも,被害弁償をできたかどうかは重要な意味を持ちます。任意保険に入っていない場合には,大きな被害弁償をすることができないのが普通であり,そのため刑は重くなる傾向があります。
任意保険,しかも全損害をカバーする保険に入っておかないと,あなたの人生が台無しになるだけでなく,被害者や遺族にも二重の苦しみを与えてしまうことになります。
私は,保険会社の代理人でも,親族に保険屋さんがいるわけでもないのですが,任意保険加入は,「走る凶器」を利用するドライバーの最低限のマナーだと思っています。
相談者の中に任意保険に入っていない方が少なからずいらっしゃるのに驚いているところです。
◆ 破産をすれば損害賠償義務は免れる?
任意保険に入っていなかった,損害賠償請求をされたけど,そんなに大きな金額を払えるわけがない,となった場合,自己破産で逃げられるでしょうか?
そう簡単ではありません。
破産には,「免責不許可事由」というものがあり,それに該当すると破産をしても債務から逃れることはできません。
人身事故による損害賠償債務は,その「免責不許可事由」に該当するおそれがあります。
また,その調査のため「破産管財人」(弁護士から裁判所が選任します)が選任される可能性が高く,その際には裁判所に納める多額の「予納金」が必要となります。
◆ 最後に
皆が自動車は危険なものであるという認識を共有できれば,と願って止みません。
最近は,自転車の事故も問題視されて来ており,多額の損害賠償義務を負うケースもあるようです。自転車も,もちろん,人にとっては「走る凶器」と言えるでしょう。自転車の保険が整備されていない現状はもどかしく思います。![]()
(なかた法律事務所)
2010年12月28日 00:20





「リフォームには集会決議が必要?」 【消費者問題】
弁護士の仲田誠一です。![]()
みなさん仕事納めはいつでしょうか?
私は,前職が銀行員であったので,仕事納めは12月30日,仕事始めが1月4日,というのが当たり前だと思ってしまっています。裁判の予定が12月 30日や1月4日に入ることはなく,物理的にはもっと休めるのですが,やはり銀行や役所が休みではない以上,仕事をしないと気持ちが悪いのです。
そのような私の気持ちは事務員さんや他の弁護士にとっては理解し難いらしいです。
結局,年末年始は他のみんなは多く休みを取り、私だけが長く働くはめになっています。![]()
今回は,前回のペット問題以外のマンショントラブルについて,少し紹介させていただこうと思います。![]()
◆ 専有部分と共有部分
マンションには,専有部分と共有部分があるのはご存知ですね。
でも,その区別については,実はなかなかややこしい問題もあるのです。
専有部分とは,区分所有権の対象となる建物部分です。居室部分ですね。
共有部分とは,専有部分以外の建物部分,その付属物,および規約で共用部分とした部分です。
廊下,階段,建物玄関,エレベーター,電気配線,ガス・上下水配管,消防設備,貯水槽,浄化槽などです。ベランダも一般的には共用部分と考えられています。
専有部分か共用部分か争われるものがいくつかあるのですが,それはまたの機会にお話します。
◆ 隔壁は共用部分ですか?
例えば,隔壁(専有部分相互間の境界部分を構成する壁)は共用部分でしょうか?
この点は,境界部分の骨格をなす中央の部分は共用部分であり,上塗り部分だけが専有部分であるとされています。隔壁は,建物を支える面もあり,建物の維持管理上,共用として管理されるべきだからです。
◆ リフォームには集会決議が必要ですか?
基本的には,管理規約の定めによることになります。
法律上の話をすると,区分所有法は,共用部分の変更に集会の決議を要求しています(17条,18条)。
したがって,勝手にした隔壁の撤去やベランダの改造などのリフォームは,集会決議を経ない共用部分の変更として,法律違反行為になるので気をつけて下さい。
この点については,バルコニーに勝手に温室を作った区分所有者に対し,管理組合がその撤去を求めて認められた例があります。
◆ 専有部分ならどう使ってもいい?
そんなことはありません。前回,「共同の利益に反する行為」を説明させていただきました。
専有部分の利用に関するトラブルとしては,前回のペット問題のほか,建物の基本構造に大きな影響を及ぼすような増改築,住居専用と定めた規約に違反してなされた事務所・営業所使用などがあるでしょう。
それらは,具体的な事情によって,「共同の利益に反する行為」と判断されるならば,法律上,差し止めや使用禁止,競売の請求の対象となります。
◆ 最後に
マンションでのトラブルの防止や早期解決には,日ごろの住民間のコミュニケーションが大事です。いうまでもありませんね。
また,ひとたび居住者による問題行動を発見したら,それが既成事実化してしまう前に,即座に対処してください。それが円満な解決の秘訣だと言えます。
さらに,管理組合の日ごろの活動に,無関心ではいけません。他の住民が無関心であることをいいことに,理事長が勝手なことをしてしまうのは珍しいことではありません。
管理組合の活性化やトラブルへの早期対処のためには,熱心で世話好きな方が1人でもいてくれれば非常に助かりますね。
もしそういう方がいらっしゃったら,うるさがらずに協力し,大事にしてあげましょう。![]()
(なかた法律事務所)
2010年12月28日 00:12





裁判離婚の話 3 【離婚問題】
弁護士の仲田誠一です。![]()
離婚をするかどうかまだ悩まれている方の法律相談を受けることもよくあります。
その場合,離婚を決意された場合の法的な説明はもちろんするのですが,どうしても人生相談の様相を呈することになります。
特にお子さんが小さい場合には悩みますね。
相談者と一緒に,
「離婚後の生活はどうするのか?」
「苦しい生活を我慢して続けることがお子さんの幸せに繋がるのか?」
「やはりお子さんにとっては両親が揃っていた方が幸せなのか?」
「あなたにとって一度しかない人生を我慢して費やしていいのか?」
「我慢し続けてあなたの心が耐えられるのか?」
などと悩むことになります。
考えは人それぞれです。そのため,自分の考えを押し付けないよう気をつけています。
ただ,私は,「あなたが幸せになることが,周りの幸せに繋がるはずだ。」と必ず伝えるようにしています。![]()
私に相談に来られるのも縁です,どういう形であれ幸せになって欲しいと願うのみです。
と言っておいてなんですが,今回も離婚の話をさせていただきます。
前々回が協議離婚の話,前回が調停離婚の話でしたので,今回は裁判離婚の話を簡単にさせていただきます。
◆ 裁判離婚とは?
離婚について同意が成立しない以上,いよいよ裁判で離婚を求めるしかなくなります。
裁判離婚とは,離婚請求を認容する判決によってする離婚です(もちろん裁判の中で,和解・認諾がされると判決によらずに離婚することができます)。
日本の法制度上,裁判離婚は,法定の「離婚原因」がないと認められません。
裁判所によって相手方の婚姻継続の意思を否定して強制的に離婚を成立させるわけですから,この場合なら強制的に離婚させてやろうという「離婚原因」が法律で決まっているのです。
◆ 法定の「離婚原因」って何?
民法770条1項に次の5つが定められています。
① 配偶者の不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みがない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
◆ 「配偶者の不貞行為」とは?
自由な意思で行った配偶者以外の者との性的交渉です。
一般的には浮気のことですが,ずいぶん前の判例で,夫から生活費をもらえない妻が生活のために行った売春行為を不貞行為であるとした例があります。
結婚すると,貞操義務が発生します。その貞操義務に違反すると,離婚原因になるだけでなく,慰謝料の支払い義務も負います。
「どこまでが貞操義務に反する行為なのか?」はまた面白い問題なのですが,機会があればご紹介します。
◆ 悪意の遺棄とは?
夫婦は,お互いに同居・協力・扶助義務を負います。正当な理由もないのに,夫婦のそれらの義務を果たさないことが「悪意の遺棄」です。
多い例が,相手を捨てて家出することでしょう。単に別居しただけでは当たりません。
◆ 3年以上の生死不明とは?
生存を示す最後の事実があった時点から3年間,生きているか死んでいるかもわからない状態が続いたことです。
生死不明の原因や責任は問われません。
失踪宣告でも婚姻関係を解消できますが,7年かかりますので,早く婚姻関係を解消したいときは,この離婚原因が意味を持ちます。
◆ 回復の見込みがない強度の精神病とは?
これは一見するとひどい法律だと感じられるかもしれません。
そもそも夫婦には,協力・扶助義務があるはずです。「配偶者が強度の精神病にかかって回復しないなら捨てていいのか?」と思われますよね。
ただ,一方で,相手と精神的な交流が全くできない中で,婚姻生活を続けることを強制するのも酷だとも言えます。法律はこの点を重視したものです。
この点,判例では,さすがに配偶者が強度な精神病であることだけでは離婚を認めていません。
病気の配偶者の今後の療養や生活について具体的な方途を講じ,ある程度前途に見通しがついた上でないと,離婚は認めない(後で触れる裁量棄却をする)としています。「具体的方途論」と呼ばれるこの考え方には,賛否両論あるでしょう。
◆ その他婚姻を継続し難い重大な事由とは
こ れまで書いた4つの離婚原因を具体的離婚原因と言いますが,最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は,抽象的離婚原因と呼ばれます。先の4つの離婚 原因がなくても,婚姻が破綻して回復の見込みがない場合には離婚を認める,それは具体的なケースにより総合的に判断する,という意味の定めだからです。
離婚請求訴訟をする場合には,通常,4つの具体的離婚原因の主張と併せて,この抽象的離婚原因を主張して争うことになります(具体的離婚原因の立証に失敗しても,抽象的離婚原因の立証が認められれば訴訟に勝てるからです)。
どのような場合にそうと認められるかを説明するのは難しいです。度重なる犯罪行為による服役や,性的異常・性的不能,DV,著しい浪費癖,過度の宗教活動等のケースがあるようですが,あくまでも具体的な事情によって判断されます。
も ちろん,自分が不貞行為をしておいて,「婚姻関係が破綻したから別れたい」,と言っても,簡単に認められるわけではありません。そのような婚姻関係破綻に 責任ある配偶者からの離婚請求を,「有責配偶者の離婚請求」と呼びます。これを説明すると長くなるので,別の機会にお話します。
◆ 法定の具体的離婚原因があると認められれば必ず離婚できるのか?
そうではありません。
法律では,裁判所は,具体的離婚原因となる事実があったとしても,一切の事情を考慮して離婚を認めないことができるとされています。
「裁量棄却」と呼ばれるものです。先ほどの強度の精神病の所で挙げた例がこれです。
◆ 裁判離婚の場合,養育費や親権者はどうなるの?
離婚と一緒に裁判所に請求すれば,裁判所が決めてくれます。別途,調停・審判を経る必要はありません。
◆ 最後に
離婚のご相談は,簡単なようで難しいです。
感情の問題がおおきい点はもちろんですし,今後の長期間にわたる生活にも関わってくる問題だからです。
離婚問題は,弁護士にとって,デリケートに扱わないといけない事件の1つであることは確かです。
3回にわたって,離婚についてざっとお話しました。
離婚にまつわる細かい話は,機会を見つけてまたお話したいと思います。![]()
(なかた法律事務所)
2010年12月27日 14:17





調停離婚の話 2 【離婚問題】
弁護士の仲田誠一です。![]()
みなさんは忘年会をいくつやりましたか?年末までまだまだ続きますね。
ちなみに,今日は事務所の忘年会です。弁護士3人,事務員3人の総勢6名の忘年会ですが,ずいぶんうちの事務所も人が増えてきたなあと思っています。
広島のいわゆる「町弁」(東京大阪の大企業向けの大規模事務所ではなく,町医者のような弁護士のことです。ドラマもありましたね。)としての適正な人員はわかりません。
ただ,私自身は,責任がある以上,受任している事件や事務所で働く仲間を常に把握したいと考えているので,これくらいがちょうどいいかなと思っています。
さて,前回は協議離婚の話を簡単にしました。
当事者で協議が整わない場合,どういう流れになるのでしょう?
今回は,調停離婚について簡単にお話したいと思います。
◆ 協議が整わなければ調停を申し立てるべき?
実は,難しい問題です。
ここで考えることは,2つあると思います。
その2点とは,①相手が協議に応じるか?,②調停が成立しない場合裁判に打って出られるかです。
調停に相手が出てこなければ調停は成立しません,今度は訴訟をするしかなくなります。
また,調停に相手が出てきても,相手方に全く譲歩する余地がなく調停の中で合意ができなかった場合も,訴訟に出るしかありません(細かく言えば「審判離婚」というものもあるのですが,あまり有用ではなくお話はしません)。
そして,訴訟をするしかなくなった場合には,法律上離婚ができる理由があるのか(離婚訴訟に勝てるのか)が問題となります。
実は,裁判上の離婚が認められる理由は法律で決まっています(次回にお話します。)そのため,そのような理由がない場合には,困ります。
「調停が駄目だった,でも訴訟に出ても勝つ見込みがないから訴訟もできません,もう少し時間をおきましょう。」,といったことになるケースもありえるのです。
ご 自分で調停をする場合には,それでよいと思うのです。しかし,弁護士が入る以上は弁護士費用が発生するわけで,相談の際には,私が受任した場合に依頼者に 本当にメリットがあるか悩む場合があります。良心的な弁護士であればそのような場合に安請け合いはしてはいけないと思っています。
そこで,じっくり話し合い,納得してもらった上で受任するようにしています。
もっとも,当事者同士では全く折り合いがつかなくても,調停委員あるいは弁護士を介して話し合うことで折り合いがつくようになるケースもあります(良心的な弁護士なら自分の依頼者に法的に落ち着くところで折り合いをつけるよう説得することでしょう)。
したがって,上のような場合でも調停を申し立てる意味はないとは一概には言えません。
◆ 調停は自分だけでできる?
調停はご自分でもできます。
た だ,ご自分で調停を行ったために,法律上請求できることをきちんと主張しないで,不利な調停を成立させてしまった例を,何件か実際に耳にしました。もちろ ん,調停委員がわからないことを教えてくれるかもしれません。しかし,調停委員はあくまでも中立的な立場であり,また当たり外れもありまして,ご自分で やって失敗するケースも残念ながら皆無とは言えないようです(もちろん調停委員のご苦労は大変なものだと聞いておりますし,ほとんどの調停委員は親切かつ 公正だと思います)。
また,強制執行の必要が出てくるケースでは,弁護士がついていた方がいいでしょう。
というわけで,個人的には弁護士についてもらった方が公正な解決が図られると思います。
ご心配,ご不安なら,是非弁護士にご依頼ください。
◆ 調停の進め方は?
調停は,1ヶ月に1回程度の頻度で期日が開かれ,調停委員が双方の言い分を交互に聞いて(相手方に遭わないでもすむよう配慮してくれます),解決を図ります。
反面,交互に話を聞かれるので,待ち時間が辛いです。
2,3回の期日で終わるようだとかなり早い解決だといえるでしょう。
合意が整ったら,いよいよ裁判官が出てきて,調停を成立させます。調停調書は判決と同様な効力があります。
ここで一点注意しておく必要があります。それは,調停の管轄(どこの家庭裁判所に申し立てればいいか)です。
原則として,相手方の住所地ということになるんです。
例えば,あなたが広島市に居て,相手方が高松市にいる場合,あなたが申し立てるべき家庭裁判所は,原則として高松です(相手方が申し立てるなら広島ということになります。)。不便ですね。ここも調停の難しいところです。
◆ 調停が整わなければ?
調停が整わなければ,またそもそも相手が出てこなければ,調停は不成立になります。
それでも離婚をしたい場合には,裁判に打って出るしかありません(審判離婚は別に置いておきます)。
次回に,裁判離婚の話を簡単にさせていただこうと思います。
(なかた法律事務所)
2010年12月27日 14:16





協議離婚の話 1 【離婚問題】
その先輩弁護士が「上海帰りのリル」って曲を歌われていたのですが,カラオケの映像に出てくる上海が今の上海とまったく違う風景でした。
車も高級車ばかり走っていました,上海ではナンバーを取るだけでかなりお金がかかるらしく,お金持ちしか車に乗れないという話を現地ガイドから聞きました。でも,その「お金持ち」が大渋滞するほど多いんです。
なお,残念ながらドイツ車が多いような気がしました。上海ではVW社がいち早く入っていたようですね。
ところで,まだ離婚について何もお話していないなと気づきました。もっと上海の話をしたいのですがまたの機会にします。
離婚には,ポピュラーなところで,協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります。
今回は,協議離婚について簡単にお話しましょう。
◆協議離婚をするにはどうしたらいい?
「そんなの知っているよ」と言われるかもしれませんが、協議離婚とは、その名のとおり当事者の協議による離婚です。
協議離婚には、①離婚意思の合致と、②届出、が必要です。つまり、当事者が離婚について合意し、その合意に基づいて離婚を届けます。
日本人には当たり前のような制度ですが、世界的に見るとそうではないんですよ。
実は,西欧ではキリスト教の関係で長らく離婚が認められなかった国もあるようです。神の許しで結婚したから別れちゃ駄目って理屈ですかね。
一方,日本では,近時の研究で,江戸時代に既に,離婚がわりと簡単に認められていたとわかってきたようです。いわゆる「三行半」って言っても,男性からの一方的なものだけではなく,今で言う協議離婚がポピュラーだったようです。日本は離婚に寛容な国のようです。
◆ 離婚届を作成したらもう覆すことはできない?
そうではないんです。
これは意外にご存じない方がいらっしゃるのですが,協議離婚に必要な離婚意思は,届出書作成のときだけでなく,届出時にも必要です。
したがって,一旦,離婚届書を作成しても,その後,一方が届出前に翻意すれば,その届けは法律上無効となります。
もっとも,相手に届出をされてしまうと後が面倒になります。そのような場合には,役所に離婚届を受理しないようにお願いできる「不受理申出制度」があります。それを利用してください。
◆ 協議離婚をする際に決めておくことは?
財産分与,養育費,子の面接交渉等々いろいろあります。簡単には説明できませんし,ケースによって決めることは違います(長くなるので,またの機会の個別にお話ししますね)。
別れたい一心で不利な約束をする方もいらっしゃるのが現実です。できれば,当人同士では決めず,弁護士等の専門家に相談してください。
また,必ず,離婚届を出す前にすべてきちんと決めてください。後でもめることになりかねませんし,「その条件なら離婚しない」っていう交渉のカードを失ってしまいます。
◆ 離婚協議書は公正証書で作成した方がいい?
公正証書で作成する意味は,証拠をより確実なものにする目的と,養育費等が支払われない場合に簡単に強制執行ができるよう手当てする目的にあります。
もちろん公正証書で作成した方がいいでしょう。
◆ 別居期間中の生活費はもらえる?
離婚協議をする段になると既に別居している方も多いでしょう。収入が相手よりも低い,あるいは子供を養っているという場合には,別居中の生活費を請求できます。
別居期間中の生活費を請求することを「婚姻費用分担請求」と言います。
夫婦双方の収入の差によって,子供の年令及び人数によって,ある程度相場が決まっています。婚姻費用は,一般的な感覚からすると十分ではないと感じてしまう金額なのですが,請求はできますので忘れずに。
支払ってもらえないときは,調停を申立て,それでも合意できない場合には審判に移ります。調停あるいは審判で決まれば,払ってもらえない場合に強制執行をすることができます。
ここで気をつけて欲しいのは,婚姻費用は別居時に遡って請求することが原則としてできないということです。それが認められるケースもあるのですが,なかなか難しいことです。
ですから,弁護士に早めに相談してください。
◆ 最後に
当事者の協議が整わない場合には,調停に進むこととなるでしょう。
法制度上,いきなり離婚訴訟をするのではなく,その前に調停を申立てることが原則となっています。
もっとも,そもそも調停を申し立てるのが意味があるか判断に迷うケースもあります。
次回以降に,調停離婚と裁判離婚について簡単にお話しようと思います。
(なかた法律事務所)
2010年12月27日 14:15





破産って恐い? 2 【借金問題】
ネット配信等でCDが売れなくなったと聞いて久しいですが、ネット配信等をあまり利用しない若年層がCDを買っているのかもしれませんね。
◆ 破産をするとみんなに知られてしまう?
破産手続き上,債権者には裁判所から通知が行きます。しかし,借金に関係のない職場や親族には連絡は行きません。
もちろん,破産手続の中で,破産者の住所氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが,見たことないですよね?普通 の方は見ないものです。また誰かが見ようと思っても,破産者はたくさんいらっしゃるので,いつ出るかわからなければ,なかなか見つけられるものではありま せん。
ただ,職場に一定年数以上勤務されている方は,退職金の見込額を裁判所に報告する必要があります,もしかしたらその関係で職場に協力をお願いする必要が出てくるかもしれません。
また,破産申立書類の準備にご家族の協力が必要な場合もあるケースもあるかもしれません。
私は,ご家族に関しては,(依頼者がどうしてもいやだとおっしゃるなら別ですが,)ご家族には相談するようお奨めしています。依頼者に経済的に立ち直ってもらうためには,ご家族に事情を知っていただき,協力していただいた方がいいと思うからです。
結論を申し上げますと,職場や家族に知られずに破産をすることは可能なのです。
◆ 破産をすると仕事を続けられない?
答えは原則としてNOです。
通常の会社員であれば破産の影響はありません。
ただ,一部の仕事だけ「資格制限」と言うものがあり,破産手続中はその仕事に就けません。
どのような仕事に就けないかは,細かく法律等で決まっています。
保険外交員や警備員など,人のお金を預ったりする職業が多いようです。
もっとも,一部の職業に資格制限があるといっても,それは破産手続が終わるまでです。破産手続が終わると法律上の制限は消えます。
自分の職業が資格制限に該当するかは,専門家にご相談ください。
◆ 破産をするとみんなに迷惑がかかる?
こちらも,答えは原則としてNOです。
もちろん,債権者には迷惑をかけることにはなります。ここで「みんな」とはご家族のことを念頭に置いています。
破産によって直接ご家族に迷惑がかかることはありません。
法律上,ご家族といっても別人格と扱われますので,あなたが破産をしてもご家族に債務が移るということはありません。
ただ,あなたがご家族等の借金の保証人になっている場合,あるいはご家族等があなたの借金の保証人になっている場合は,別です。
あなたが破産をする際には保証債務も債務として手続に乗せる必要があります。具体的には保証している相手方(たとえばお父さんの銀行からの借金に保証をして いる場合にはその銀行)に通知をすることとなり,(先の例では銀行からお父さんに対し)新たな保証人の追加などを要求されることもあります(銀行とお父さ んが交渉することになります)。
また,あなたが破産をするということは,当然,あなたの保証人に対し債権者から請求が行くことになります。
さらに,不動産をご家族と共有している場合には話が複雑になるでしょう。不動産の維持は,非常に込み入った話になり,ケースごとに判断する必要があります。弁護士などの専門家とじっくりご相談してください。
◆ 最後に
みなさんが思っているほどは,破産は恐くないということをお話しました。
もちろん,破産を積極的に勧めているわけではありませんからね。
ただ,破産でしか救われない方もたくさんいらっしゃるのが現実です。
借金でご苦労されている方は,是非早く弁護士等にご相談ください。あなたにあった解決策を考えましょう。
みなさんが思っているほど「弁護士も恐くない」ですよ。
(なかた法律事務所)
2010年12月26日 14:13